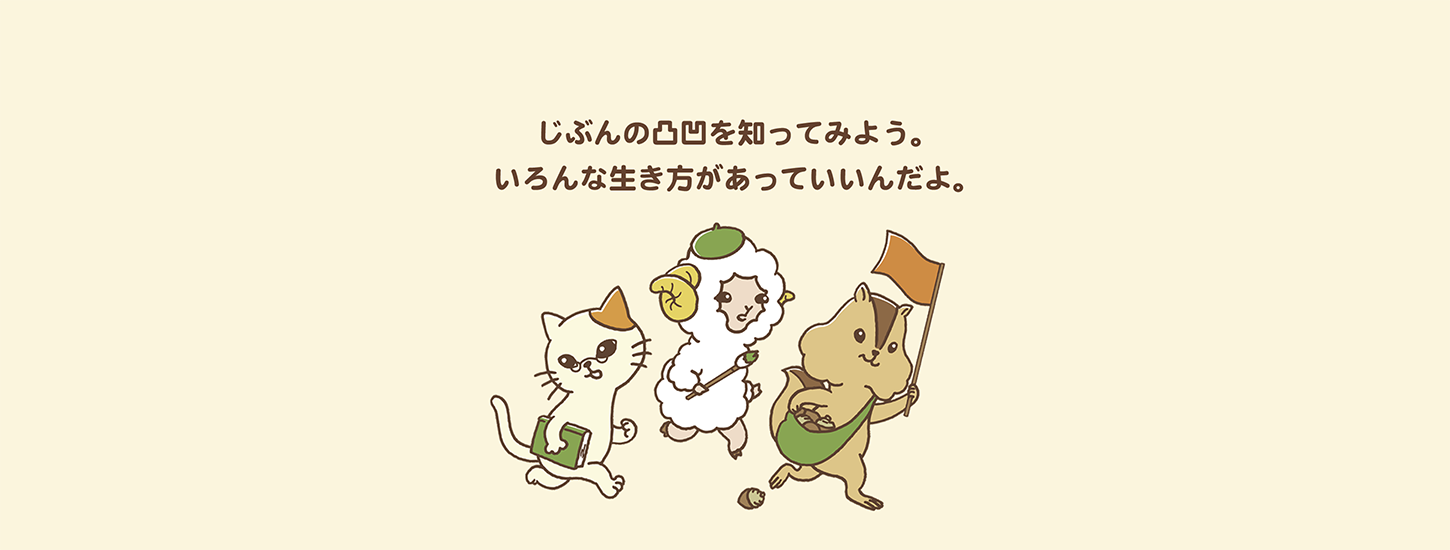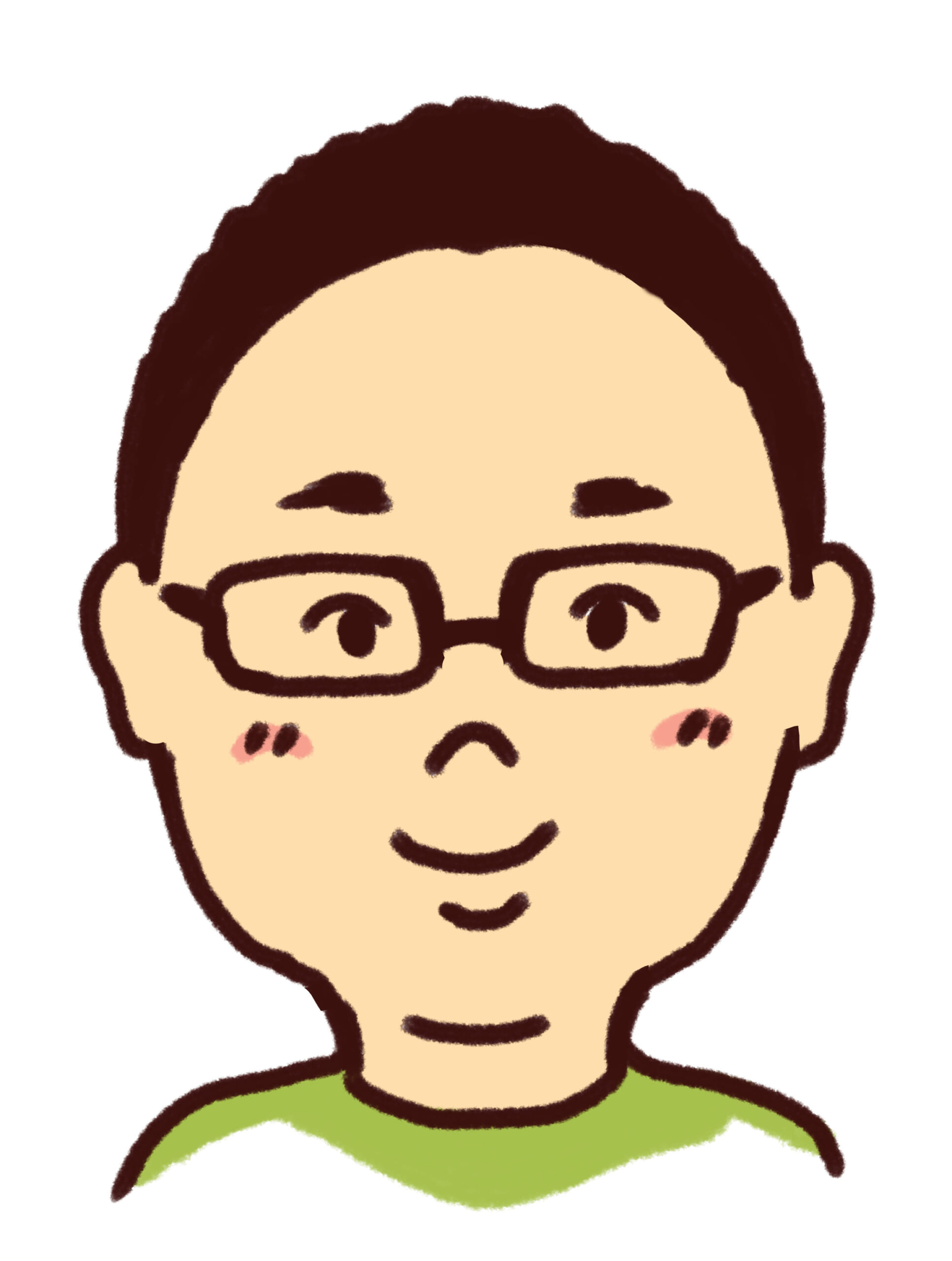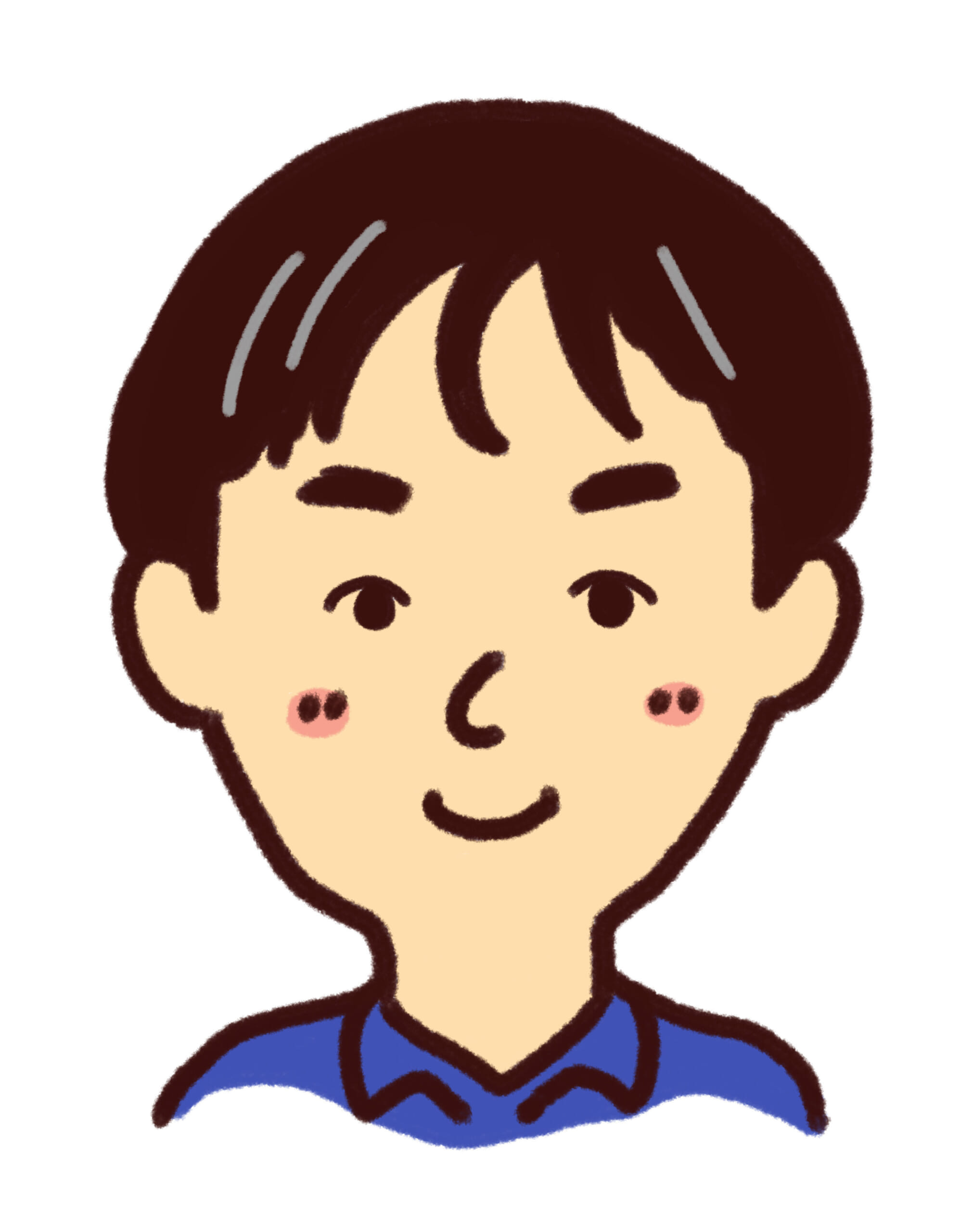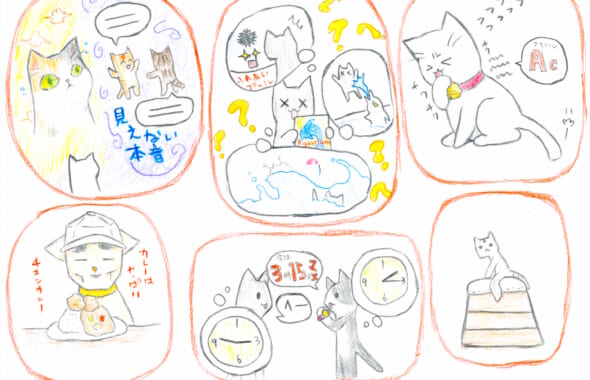発達性協調運動症(DCD)とは?
発達障がいと聞いて、皆さんは何を思いついますか?
おそらく、注意欠如・多動症(ADHD)、限局性学習症(SLD)を上げる方が多いと思います。
ここで、発達性協調運動症(DCD)を上げる方は少ないのではないでしょうか。
あまり知られていませんが、DCDの有名な方としては、ハリーポッターの俳優ダニエル・ラドクリフさんがおられます。
発達性協調運動症(DCD)とは?
発達性協調運動症(Developmental Coordination Disorder: DCD)は、
いくつかの動作を協調的に行う事が苦手で、「手先の不器用さ」や「運動能力の低さ」が目立つ状態をいいます。
特性のあらわれ方は子どもによって異なりますが、「自分の体の感覚をうまくつかめていないこと」が主な原因と考えられています。
DCDの人はどれくらいいるの?
小児期のDCDの有病率は、日本人の約5~10%といわれています。
小学校の30人学級であれば、2,3人はいる計算になります。
そして、DCDは、注意欠如・多動症(ADHD)の30~50%、限局性学習症(SLD)の50%が発症しており、他の発達障害と併存する可能性が高いのが特徴です。
DCDの発達特性
「身体的には問題ないが、乳幼児期から運動発達が遅く、人並み外れて不器用・極端に運動が苦手な状況」が特徴です。
協調とは?
「見る、触る」といった感覚、筋肉や関節の感覚、平衡感覚など、様々な感覚の情報を整理し、運動として身体を動かす脳の機能です。
運動やスポーツに限った話ではなく、
衣類の着脱、食事の時の箸の使い方といった日常生活動作や書字、ハサミの使い方、折り紙などの手指を使った細かい作業、そして、縄跳びやボール運動に加え、姿勢の保持、物を運ぶ、ボディ・イメージなど学校生活や日常生活の多岐に渡り重要なキーワードとなっています。
<乳児期>
- ミルクを飲むときにむせやすい
- 寝返りがうまくできない
- ハイハイがぎこちない
<幼児期>
- 階段の昇り降りが苦手
- はさみがうまく使えない
- 着替えが遅い、難しい
<学童期>
- 体操やダンスで手足の動きがバラバラ
- 縄跳びや鉄棒ができない
- ボール運動が苦手
- 両手を使う楽器の操作が不得手
- ボタンかけに時間がかかる
- エプロンや靴ひもを結ぶのが苦手
- 文具やお箸を 上手に使えない
- 筆圧が強すぎる
- マスや行からはみ出る
- 手足に麻痺はないが、動きがぎくしゃくしているように見える
<青年期・成人期以降>
- 第二次成長を受け入れにくい
- 授乳姿勢がうまく維持できない
- オムツを替える際の手際が悪い
- 沐浴指導をしてもうまく赤ちゃんを支えることができない
- 動き回る子どもを静止できない
- 手をつなぐことを続けてできない
- 食べさせ方のタイミングが子どもとあっていない
DCDと運動能力
大人も子どもも、多くの人が、毎日立ち上がり、毎日歩き、時には走って、また座った姿勢を保って生活しています。
また、スポーツなどでは、目と手や、手と足など、複数の箇所を同時に動かす「協調運動」も求められます。
例えば、キャッチボール。
投げられたボールを目で見て、ボールの軌道を予測し、到達予測地点に手を伸ばし、ボールの到達と同時に手を握る、という、複数の運動が関係しています。
目で見ること、手を動かすこと、どちらが欠けてもうまくボールはキャッチできません。
目と手の「協調」があって達成できる運動なのです。
DCDは、この「協調」が苦手なので
手と足を同時に動かすべきところでぎこちなさが生まれたり、目で見た情報にあわせて手足を動かしたりすることにつまずいている可能性があります。
また、手や指を使った細かく精密な動作を必要とする運動のように、大きい物を扱うよりも、小さい物を扱う方が難易度は高くなります。
字や絵を書いたり、箸を使ったり、積み木で遊びやビーズ遊びなどは、難しい運動になります。
DCDの療育や支援方法
8つのポイントをまとめてみました。
1.自己肯定感を育みましょう
手先の作業や運動は、その子ども自身にも、周囲からもできていないことが一見してわかってしまうため、自信をなくし、意欲や自尊心が低下していまいます。
また、根性論での叱責、不適切な反復練習は逆効果になってしまいます。
その結果、不登校などにつながってしまうことも多いのです。
支援方法次第で二次障害につながってしまう可能性は非常に高いですので、注意しましょう。
2.親子での遊びを取り入れる
すべての運動の基礎となるバランス感覚を愉しみながら鍛えられます。
ひこうきや、手押し車等を親子で一緒に遊ぶことで、普段回転や逆さまを怖がるお子様も愉しめるかもしれません!
お父さん、お母さんという「絶対的安心」のもと、非日常感覚にチャレンジしてみましょう
3.全身運動を取り入れる
くまさん歩き、リズム運動をすることで、全身を協調して動かしましょう。
特にリズム運動は、人の動きを目で見て自分の動きをコントロールしたり、リズムや音楽を耳で聞いて表現したりする活動であるため、ボディイメージを習得する機会となります。
4.バランス感覚を育む
トランポリン、ブランコ、けんけん運動、片足ジャンプ等て揺れを体験し、バランス感覚を養います。
発達障害児は感覚が鈍感だったり敏感だったりすることが多いです。
例えば、トランポリンで飛び跳ねることで重力の変化を体感でき、感覚情報を上手く取り込むトレーニングになります。
楽しみながら、知らず知らずの内に感覚が養われます。
5.道具で運動する
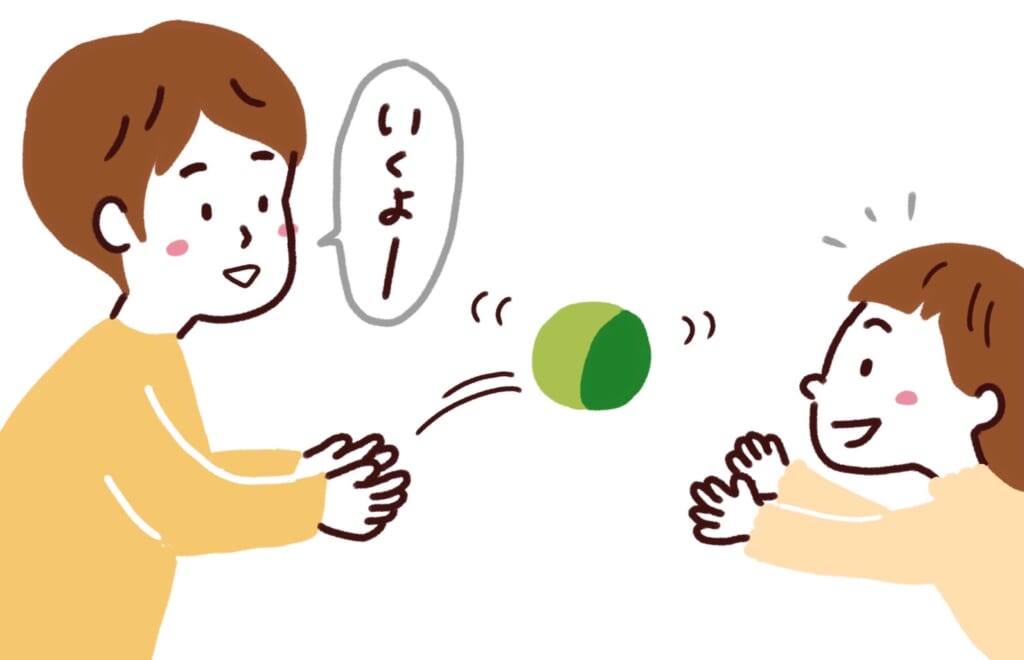
大きめのボールでキャッチボール、ゴムとび等、道具を使って運動しましょう。
道具を使うだけでも、協調が必要です。さらに運動もするので、協調することがたくさん出てきます。
とても難しい運動となるので、スモールステップで楽しんでおこないましょう。
6.感覚統合を取り入れる
じゃんけん、のりをぬる、粘土遊び、スライム作り等の感覚統合をしましょう。
自分の体を使ったり、道具を使ったり、人とコミュニケーションを取ったり…私たちは、無意識のうちに周りの環境とうまくかかわっています。
これは脳に入ってくるいろいろな感覚を、うまく整理したりまとめたりすること、即ち感覚統合ができている状況です。
7.ビジョントレーニングを取り入れる
Milesら(2015)が発表した不器用な子どもたちに関する報告(Miles CA, Wood G, et al.: Quiet eye training facilitates visuomotor coordination in children with developmental coordination disorder. Res Dev Disabil40:31-41, 2015.)があります。
不器用さを主体とする発達性協調運動障がいの子どもたちに、ボールを投げる・キャッチする課題を実施してもらい、そのときの運動パフォーマンスを分析しています。
結果のなかで興味深いのは、運動そのものは指導せず、「どこを注視すべきか」を教えるアプローチをしたグループでも、ボールをキャッチする動作の質が上がったという事実です。
つまり、「見る力」に関するトレーニングを行っただけで、運動の仕方にも効果が及びます。
8.理学療法による支援
姿勢制御のためには,体幹筋全体が常に協調し,その瞬間の状態に適応して活動する必要があります。
理学療法をおこない、運動の正確性,筋の適切な収縮力と活動するタイミングを向上させることで協調性のある動きを獲得することを目標にしましょう。
「不器用さ」をDCDと捉えることでのメリット
発達障害と捉えることによって、2016年に施工された「障害者差別解消法」によって、「合理的配慮」が求められるようになります。
例えば、学校であれば、先生が子どもがこなせるように課題を示したり、環境調整をしたり手助けするということができます。
また、医療や療育を受けることにより、本人の障がい特性を理解する一助になります。
また、運動の支援を受けることができます。
最後に・・・
まだDCDは、研究中であり、これから発展していくものである。残念ながら、現状では、まだ不明なところも多く残っています。これからの研究に期待します。
そして、私たちはDCDのことを、広げていきましょう。
<参考文献>
金子書房『発達性運動障害「DCD」不器用さのある子どもの理解と支援』 監修/辻井正次・宮原資英 編著/澤江幸則・増田貴人・七木田敦